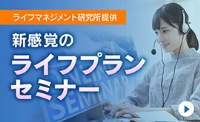9月の風の便り
新型コロナの変異株による感染拡大がなかなか収まりません。間もなく世界で感染拡大が始まって2年が経過しようとしていますが、2年目の現在はワクチン接種がワクチンの遅れなどにより思うように進んでいないのが実態です。毎日ニュースで「コロナ感染者○○名」と報道されますが、これだけ連日連夜情報が流されると、脳に不安と恐怖心が深く刻み込まれてしまっているのではないかと思います。ある学者が「コロナウィルスも深刻だが、情報による不安ウィルスも深刻になっている」の述べてましたが、まさにそうだと思います。
■PCR検査とは?
そもそもPCR検査陽性=コロナ感染者という方程式は正しいのでしょうか?まずはこの検査の経緯を知っておきたいところです。PCRとは「ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)」の略称です。このPCRは、米国のキャリー・マリス博士によって発明された技術です。博士は1993年にPCR開発やその他の功績からノーベル化学賞を受賞し、2019年に亡くなりました(死因は不明?)。
■生前の同博士のコメント
現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを検査する初期検査としてPCR検査が行われていますが、博士は生前にPCRについて次のようにコメントしています。「PCRを感染症の診断に用いてはならない」と。
そもそもPCR法とは、遺伝子(DNAやRNA)配列を可視化するために遺伝子(DNAやRNA)の一部を数百万から数億倍に複製する技術です。ウイルスそのものを検出するのではなく、唾液などのサンプルの中に新型コロナウイルスの遺伝子の一部があるかを見て、ウイルスの存在を間接的に判断するという方法です。そのため、遺伝子配列が全て一致していなくても、遺伝子の一部さえ合致していれば、他のウイルスでも検出し、陽性反応を示します。さらに、複製回数(サイクル数)によっても陽性率が大きく変化するといわれています。また、そのウイルスの特性まではわからず、感染力のない微量なウイルスや、死んだウイルスでも存在が確認されれば陽性となってしまいます。
■コロナ以外にも反応する?
実際にPCR検査キットの中には、インフルエンザ、マイコプラズマ、アデノウイルス、RSウイルス、クラミジア等に反応する可能性が記載があり、 「コロナウイルス感染症の診断の補助としての使用を意図したものではない」 「研究用としてのみ使用し、診断手順に使用するためのものではない」 との記載があるようです。また感染について、例えばインフルエンザウイルスでは、粘膜等にウイルスが付着しているだけでは感染と言わず、細胞内にウイルスが入り込んで増殖した状態ではじめて「感染」と診断されます。
■増幅回数で陽性反応が変わる?
PCR法は遺伝子を数億倍に増幅するため、実際には数個のウイルスが付着しているだけの人も「陽性」になります。つまり、PCR検査で新型コロナウイルスのみを判定できるわけではないため、「PCR陽性」=「新型コロナウイルスに感染」ではないということになります。
前述の通り、PCR検査はインフルエンザウイルスを含む他のウイルスでも陽性反応が出てしまいますし、サイクル数の設定を変えることで陽性率が格段に高くなる、恣意性の高い検査方法です。またPCR検査はサイクル数を増やす毎に、より少ないウイルスでも陽性となります。
例えば、10サイクルだとウイルスの数は1000万個以上で陽性、20サイクルにすれば10万個以上で陽性、さらに30サイクルでは1000個以上で陽性、40サイクルになるとわずか10個以上でも陽性になるといわれています。
ちなみに、日本の場合、国立感染症研究所の「病原体検出マニュアル(令和2年3月19日)」では、判定するのに必要なサイクル数を45サイクルとしています。つまりウイルスが10個程度存在すれば陽性となるようです。みなさんはPCR検査についてどのようにお考えでしょうか?
■情報は鵜呑みにしない
コロナ問題を取り上げましたが、コロナ問題に限らず「ネット社会」は情報があふれています。テレビやマスメディアの情報すら正しい情報かどうかわからないことが多い時代でもあります。ですので個々人で客観的な判断基準を持つことが必要な時代になってきています。
コロナ問題でも個人にとって重要なことは、自粛すること以上に「個々人で免疫力を上げていく」ことにつきます。これが私なりの結論です。「栄養バランスを整え、体力を維持し、健全な精神性と深い睡眠を確保する」事こそやるべきことです。ここまで来ると、「コロナウィルスの収束」よりも、「コロナ問題の収束(複数の方法を組み合わせること)」こそ我々が目指さなければならないことのように思います。
情報は自分にとってのメッセージ性(意味)を考え、そしてしっかり行動することです。新しい時代へシフトしようとしている今だからこそ、自分を見失わないよう生活していきましょう。